.jpg)
やや小型でレモンの香りが爽やかです
レモンタイム(Lemon thyme)は、
シソ科の多年草であるタイムの仲間です。
レモンタイムは名前のようにレモンの香りのするタイムです。
コモンタイムと同様に、料理やティー、ポプリにもできます。
ゴールデンレモンタイムという品種もあり、
明るいグリーンの葉に、黄色い斑が入るので、
とても明るい印象です。
■レモンタイムの育て方
・栽培環境
レモンタイムは、日当たりがたいへん好きで、
耐陰性もややあり、日陰でもどうにか栽培できます。
耐寒性もあり、暑さにやや弱いところもあるため、
一日中、陽の当たる場所ではなくても、問題なく育ちます。
ただし、あまり日陰で栽培すると、香りが弱くなることがあるので、
料理やティーに使う場合は、日当たりの良い場所で育てましょう。
庭造りのカラーリーフとして使う場合は、
半日陰などの場所で使うと、明るい葉色が活かせます。
日当たりの良いところでも、半日陰でも、
風通しの良い場所を選ぶようにしましょう。
・植え付け
3月~4月か9月~10月が、植え付けの適期です。
地植えであっても、鉢植えであっても、
排水性の高い土を好みます。
用土は小粒赤玉土7に腐葉土3を混ぜたものを使うか、
市販の培養土やハーブ専用の培養土を使用します。
培養土などの場合、水はけをより良くしたい場合には、
赤玉土やパーライトを適宜混ぜて、試してみてください。
植え付けた後は水をたっぷり与えます。
乾燥気味の土壌を好むレモンタイムです。
しかし、植え付け直後は根付いていませんので、
乾燥させ過ぎないように管理します。
・植え替え
レモンタイムは生育が早い植物で、鉢などの容器栽培をしていると、
根が鉢に一杯になってしまい根詰まりを起こしがちです。
鉢の底から根が見えたり出ていたら、植え替えの時期です。
1年~2年に1回は植え替えるようにすると丈夫に育ちます。
1~2号ほど大きい鉢に植え替えますが、
大きな鉢にしたくない場合は、
株分けをして株を小さくして、同じ鉢に植え直します。
植え付け後と同様、根付いてませんので、
しばらくは乾燥させないように注意します。

ハーブティーも楽しめます
・水やり
レモンタイムは、湿気た環境が少し苦手ですので、
土の表面が乾燥してから、
じゅうぶんに水をあげるようにします。
土が湿っている状態で水を与えてしまうと、
湿気た環境になり、蒸れて株元から枯れてきたり、
根腐れを起こす原因になりますので注意しましょう。
冬はさらに水を要求しません。
雨のあたる場所で育てている場合は、雨だけで十分です。
軒下で管理していたり、雨が長く降らずに土が乾くのであれば、
土が乾燥してから水をあげるようにします。
・耐寒性
耐寒性はありますので、特別な防寒対策は必要ありません。
ただし、霜にあたると葉が黒くなって傷みます。
春になれば新芽が出て葉が展開してきますが、
気になる場合は、マルチなどで防寒してください。
・耐暑性
レモンタイムは、ある程度の暑さには耐えますが、
猛暑には、根が傷んで枯れることがあります。
また、蒸れにも弱いので、できる限り風通しの良い場所で育てます。
レンガやコンクリートなど蓄熱性のあるものには、
スノコを敷くなど、直に触れないように育てましょう。
.jpg)
ゴールデンレモンタイム C)花みどりマーケット
葉色が美しくガーデニングにも人気のタイムです
・施肥
肥料はほとんど必要としません。3月~10月の生育期間に、
2ヶ月に1回のペースで緩効性の肥料を与えます。
真夏と冬は肥料を必要としませんので、与えないようにします。
肥料をやり過ぎると、せっかくの香りが弱くなります。
・剪定
梅雨に入る前に必ず切り戻しをします。
梅雨に入ると気温も上がり、湿度も上がり蒸れやすくなります。
短く刈り込むことで蒸れを防ぐことができます。
枝が混みあっている場所があったら、
間引くように剪定すると良いでしょう。
10月頃、霜が降りる前にも切り戻しておくと、
春に新しい枝葉が伸びてきます。
上記以外にも、収穫をかねて枝が混んでいる場所を、
すくように枝を間引いておくと、株姿が整います。

お料理にも活躍します
・増やし方
レモンタイムは、挿し木か株分けで増やすのが簡単です。
◎挿し木
挿し木の場合は、長さ10~13cmほどの挿し穂を作ります。
枝の下から半分ほどまで葉を取り、
切り口をカッターなどで再び斜めに切って、
水の入ったコップなどに挿して1~2時間ほど水上げをします。
平鉢に、赤玉土、バーミキュライトを入れて湿らせ、
箸などで一回穴を開けてから、水上げした挿し穂をそっと挿します。
半日陰か明るい日陰で、乾燥しないように管理します。
ときどき霧吹きで水をかけてあげるのも効果的です。
>>挿し木(挿し芽)の方法 画像つき
◎株分け
株分けの場合は、鉢から株を抜き、土をていねいに落とします。
根を手でほぐしたら、あまり小さくならないように株分けをします。
株分けしたものを植え付けたら、しっかりと水を与えます。
根がダメージを受けているので、新しい枝葉が伸びてきても、
しばらくは収穫せずに株を育てるようにしましょう。
■病害虫
レモンタイムには、特に気にする病害虫はありません。
■参考
・タイムの育て方
・フォックスリータイムの育て方
・クリーピングタイム(ワイルドタイム)の育て方
・タイムの種類
・シルバータイムの育て方
-5157c.jpg)
.jpg)
.jpg)

-88538.jpg)
.jpg)
-d6047.jpg)
.jpg)
.jpg)
-a4008.jpg)
-43324.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.JPG)

-2bdf7.jpg)
-39dc2.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








.jpg)
-bae33.JPG)






-9a54a.jpg)

-6e656.jpg)
-906da.jpg)
.jpg) アカバナ
アカバナ フウリンブッソウゲ
フウリンブッソウゲ  オレンジフラミンゴ
オレンジフラミンゴ.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-thumbnail2.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)
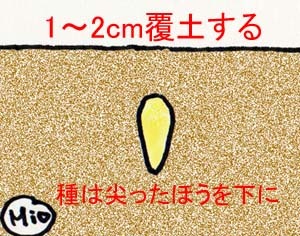
-thumbnail2.jpg)
-7ba58.jpg)
-138c1.jpg)
-thumbnail2.jpg)
.jpg)



.jpg)


-67918.jpg)
.jpg)
.jpg)
-6c145.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)